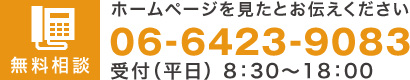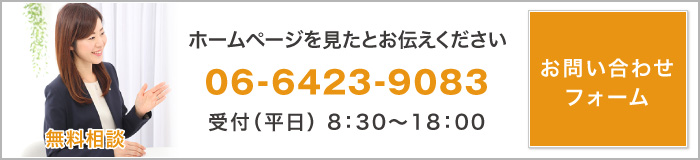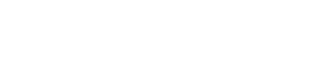遺言書を作成することによって多くのメリットがある旨は、遺言書作成のメリットにてご紹介させていただき、遺言書作成をお勧めさせて頂きました。
しかし、メリットにとどまらず、「遺言書の作成を絶対に作成すべき」場合もあるのです。
では、具体的に「遺言書の作成を絶対に作成すべき場合」とはどのようなケースを言うのでしょうか。
以下、事例形式でご紹介致します。
このページの目次
事例1 法定相続人以外の人に財産を残したい場合
長年連れ添っている内縁関係の相手に財産を残した場合、内縁は法律上の婚姻関係ではないので、相続権はありません。
また、既に他界した長男の嫁に財産を残したい場合も、長男の嫁は法定相続人ではないので、相続権がありません。
このように法定相続人以外の方で縁があった人やお世話になった大切な人に財産を残したいケースには、その人に財産を「遺贈する」旨の遺言が必要となります。
遺言書は、故人の遺志を残すものです。
よって、遺言を残すことでその財産の帰属先を自由に決められるのです。
(※但し、遺留分については排除できません。遺留分については遺言書作成のメリット)
逆を言えば、遺言書を残さない限り、基本的には相続人以外の者に財産を残すことはできないので注意が必要です。
事例2 法定相続分と異なった割合で財産の残したい場合
勝手に家を出ていった長男よりも、自分の身の回りの世話を親身にしてくれた長女に法定相続分より多めの財産を残したい。
そのような場合にも、遺言書がない場合には長男・長女ともに同じ割合での財産を取得することになってしまいます。
自分の意思通りに財産を取得させたいのであれば、遺言書に長女に多くわたるように、配分を指定しておく必要があります。
ただし、長男・長女の間で争いになる可能性もありますので、遺留分を考慮したものにする(遺留分)、などの方策を講じることによって争いを避けるようは配慮も必要です。
事例3 相続人同士の仲が悪い場合
相続人同士の仲が悪い場合、大きなトラブルになることも多く見受けられます。
遺産分割協議では全員の同意がないと財産を引き継ぐこともできないので、時間ばかりかかってしまい、最終的には裁判になったりするなど、気に病むこともあるでしょう。
事前に遺言書を残しておき、相続人を指定しておくことで相続人間の話し合いを経ることもなく、スムーズに進めることもでき、争いが大きくなることも防ぐことができます。
事例4 事業を継続させていきたい場合
被相続人の方が事業を営まれていたケースにおいて、その株式をご自身で保有されていた場合には、相続により会社の株式が各相続人の共有となってしまい、その後の経営権争いなど、経営に支障が出ることも十分考えられます。
いわゆる同族会社における事業承継の問題と言われるものです。このトラブルが生じると解決までの間経営も滞ることになり、取引先や従業員へも迷惑をかけ、やっと解決したころには、利益も信用も回復しえない状態になってしまうという事もあり得ます。
経営者としてそのような事態は絶対に避けるべきです。遺言書により株式や経営権の分割方法を指定することで後継者にスムーズな事業承継ができ、事業をより発展・継続させていくことができます。
事例5 主な相続財産が不動産である場合
不動産は預金等の金銭と異なり「物」であるため、簡単に「分ける」ことができません。不動産の他に預金等の分配しやすい財産が多い場合には、長男へ不動産を、次男三男へ不動産と同等の金額の預金を分ける、といった方法も取れますが主な相続財産が不動産である場合、このような方法がとれず、相続人間で遺産分割協議をしても、うまく合意ができず、争いに発展してしまうことも多くあります。
最悪の場合、協議が整わない為、法定相続により不動産を共有引継ぎとしたものの、売却しようにも全員の合意が整わず、売却することもできず空き家のまま放置される、といった事態にもなりかねません。
それがご自身が長年住まわれてきたご自宅であったなら、なおさら残念です。
不動産の引き継ぎ先や分割方法を遺言書で指定しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、残された不動産を有効に活用してもらうことができます。
事例6 相続人がいない場合
相続人が誰もいらっしゃらない場合、相続財産は国庫に帰属します。
「国」のものになってしまうのです。
あなたさまが長年生活されてきた中でお世話になった方、また、これからより発展して欲しいと願う団体、興味が少しでもある事業、趣味の団体、お心当たりはありませんか?
こういった相続人でない方や、個人でない、団体や協会へご自身の大切な財産を「遺贈する」ことによって譲ったり、寄付したりすることができるのです。
遺言書を残しておくことで、ご自身が本当に財産を渡したい相手へ、その財産が引き継いでいくことができるのです。
事例7 未認知の子どもがいる場合
生前には事情があり、認知していない子どもがいるのに、それを家族に伝えることができかった場合、遺言書で認知することによって、その子どもにも財産を相続させることができます。
いわゆる「遺言による認知」によって、その子を自分の相続人とすることができるのです(遺言で決められること)。
生前には何もしてあげられなかったが、せめて遺産は渡したい、との秘めた思いも遺言によって実現することができるのです。
以上、「遺言書の作成を絶対に作成すべき場合」についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか。
遺言書は、故人の遺志を残すものです。
よって、遺言書を作成するか否かは、遺言者の自由です。しかし、遺言者の為だけの制度ではないとお気づき頂けたのではないでしょうか。
遺言書は、大切なご家族・縁故者の為の制度でもあるのです。
遺言書の作成について、ぜひご検討いただければと思います。